このブログでは、教育という大きなテーマを、僕自身の視点から深掘りしていきたいと思っています。特に、日々特別支援教育に携わる中で感じる素朴な疑問や、ハッとさせられる発見を皆さんと共有できたら嬉しいです。
仕事のことだけでなく、プライベートでは妻と3歳の娘、2歳の息子、そして愛犬のポメラニアンと賑やかに暮らしています。子育てやワンちゃんとの触れ合いから生まれる、ささやかな気づきや感動も、この「まなびとくらしのノート」で綴っていきますね。
さて、今日のテーマは、少し真面目な話から始めさせてください。
日本が高度経済成長期を迎えていた1960年代。当時、「障がい者」と呼ばれてきた方々は、労働力として社会参加することが強く期待されていました。学校教育も、将来の職業選択に直結する競争・能力主義的な側面が色濃く出ていた時代です。
そんな中、糸賀一雄さんと田中昌人さんの研究から生まれたのが、**「発達保障論」**でした。これは、「障がい」を多角的に捉え、社会全体でそのあり方自体を変えていこうとする画期的な考え方です。しかし、この発達保障論が「養護学校義務化」(1979年)の流れと結びつく中で、「分離教育」と「共生教育」という、さまざまな対立を生む複雑な状況が生まれていくことになります。
この夏、僕は改めて**「インクルーシブ教育システム」**の概念について、資料を読み込み、深く学ぶ時間を持ちました。その中で、これまでの特別支援教育の歩みをたどり、これからの教育のあり方を考えることへの熱い思いが込み上げてきたんです。
そして、仕事をする中で、「障がい者」という概念そのものが、時に社会に差別や理不尽を生み出しているのではないか? という疑問を抱くようになりました。このことについても、皆さんと一緒に深く考えていきたいと思っています。
これから「まなびとくらしのノート」を通して、これらのテーマを皆さんと一緒に学び、考えていけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします!
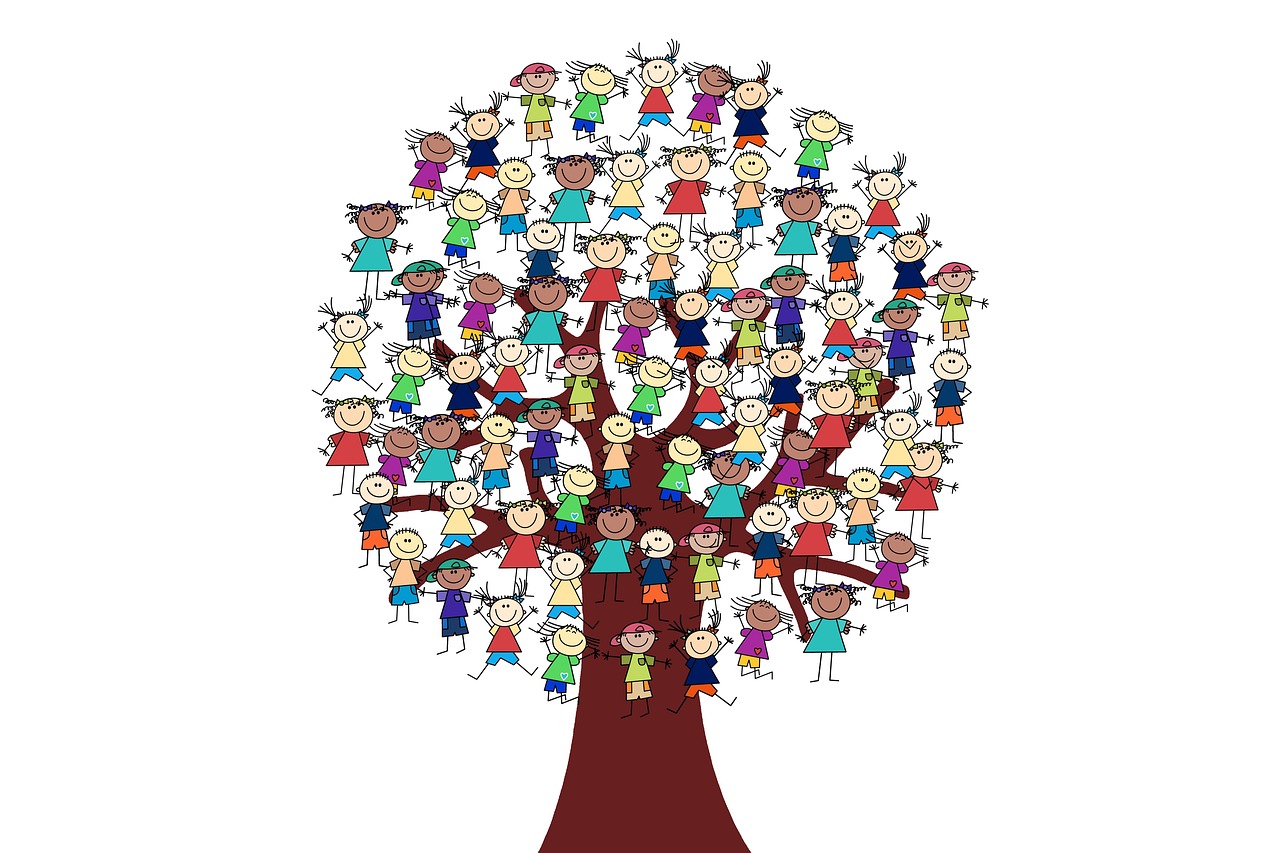

コメント