障害者雇用、その未来を考える
こんにちは!皆さんは、「障害者雇用」と聞いて、どんなことを思い浮かべますか?
義務だから? 社会貢献? それとも、少し難しい話だと感じますか?
今回は、学校を卒業して、いざ社会へ踏み出す障害のある方々が直面する「就労」というテーマについて、企業側と働く側の両方の視点から、わかりやすく解説していきたいと思います。
企業側の視点:障害者雇用は義務?それともチャンス?
法定雇用率という「ルール」
まず、企業には障害者雇用促進法という法律で定められたルールがあります。従業員の数に応じて、一定の割合で障害者を雇用しなければならないというものです。これを法定雇用率といいます。2024年4月からは、民間企業の法定雇用率は**2.5%**に引き上げられました。
この目標を達成できない企業には、障害者雇用納付金というお金を納める義務が発生します。これは「雇用できなかったことへのペナルティ」とも言えるでしょう。
深刻な人手不足、多様な人材の活用がカギ
少子高齢化が進み、日本の働く人口はどんどん減っています。このような状況で、企業が成長を続けるためには、多様な人材の力を借りることが不可欠です。外国人や高齢者、そして障害のある方々の力を活かすことは、単なる社会貢献ではなく、企業が生き残るための重要な戦略の一つとなっています。
障害のある方が持つ独自のスキルや発想が、新しいサービスや商品を生み出すきっかけになることもあります。
企業のイメージアップにもつながる社会貢献
障害者雇用は、企業の社会的責任(CSR)を果たす上で非常に重要です。障害のある方が働きやすい環境を整えることで、「この会社は社会に貢献している」という良いイメージが生まれ、会社の信頼度やブランド価値が高まります。
働く側の視点:自分に合った働き方を見つける
一般就労と福祉サービス、どちらを選ぶ?
障害のある方が働く場所を探すときには、主に2つの選択肢があります。
- 一般就労: 障害のない方と同じように、一般の企業に就職して働くスタイルです。
- 障害福祉サービス事業所での就労: 自身の体調や特性に合わせて、サポートを受けながら働くスタイルです。就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)など、様々なサービスがあります。
自分に合った働き方を見つけることが、長く働き続けるための第一歩になります。
安定した生活と職場定着
働き始めることと同じくらい大切なのが、職場に定着することです。企業側の理解や、本人の障害特性に合った働き方の調整が不可欠です。
また、生活面では、障害者年金を受給しながら、一人暮らしをしたり、グループホームで生活したりするなど、その人らしい自立の形を築いていくことも大切です。
まとめ
一昔前に比べると、障害者雇用に関する企業の取り組みは大きく進んでいます。しかし、まだ「障害者雇用は難しい」という偏見を持っていたり、雇用に前向きでない企業も存在します。また、仕事内容が合わずにすぐに辞めてしまうなど、職場に定着できないという課題も残っています。
より多くの人が自分らしく働ける社会を目指して、私たち一人ひとりの意識を変えていくことが重要です。


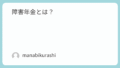
コメント