「共生」と「分離」:日本の教育はどこへ向かうのか?〜カナダ・ハミルトン市の事例から考える〜
みなさんは「インクルーシブ教育」と聞いて、どのようなイメージを思い浮かべるでしょうか?
カナダのオンタリオ州ハミルトンにおけるフル・インクルーシブ教育の実践は、私たちが改めて「共に学ぶこと」の意味を考える良いきっかけを与えてくれます。ハミルトンでは、「個人の成長の限界は、未知で制限されるべきでない。」という理念が掲げられています。
ハミルトンが目指す「共生」の教育
ハミルトンの教育は、子どもに障がいやその他の要因による制限があっても、その子を分離するのではなく、**「どのようにしたらよいかということに集中すること」**に重きを置いています。
そのために、「彼のニーズや生い立ち、経験はどのようなもので、学習上の困難は何でどのような配慮が役に立つか」という評価・診断的な処方アプローチが教える側と学習に必要だと定義されています。これは、障がいそのものを問題とするのではなく、その子の特性を理解し、共に学ぶための具体的な方法を考えるという姿勢です。
ハミルトンでは、この理念を実現するために、具体的に以下の3つのアプローチを組み合わせています。
- 通常学級+合理的配慮
- 通常学級+特別支援アシスタント
- 通常学級+追加の支援(1日15〜30分程度)
これらの支援を組み合わせることで、「機会の均等と個別化」というインクルーシブ教育における大きな課題を両立させています。これは、すべての子どもが同じ教室で学ぶ機会を確保しつつ、それぞれに必要な個別的なサポートを提供する**「包摂的個別対応」**の在り方なのではないでしょうか。
この実践は、障がいのある子どもを「特別」な存在として分けるのではなく、「共に学ぶ」ための環境をどう整えるかという視点の重要性を教えてくれます。
日本の教育現場における「分離」のアプローチ
一方、日本の教育現場では、障がいへのアプローチとして「専門性」が重視される傾向があります。特別支援学級や通級指導教室は、専門的な知識を持った教員が、子ども一人ひとりの障がいに応じた指導を行う場として発展してきました。
しかし、この専門性を追求するあまり、結果的に子どもたちが**「通常学級」から分離される**形になってしまっていないでしょうか。
「分離」がもたらす光と影
専門的な支援は、子ども一人ひとりの困りごとに寄り添い、確実な学習効果をもたらすという大きなメリットがあります。しかし、その一方で、次のような問題も生じかねません。
- クラスメイトとの分断: 多くの時間を異なる教室で過ごすことで、共に学び、遊び、成長する機会が失われてしまう。
- 社会との分断: 将来、障がいのある人とない人が共に生活していく社会の中で、子ども時代に分断を経験することで、お互いを理解する機会が少なくなる。
日本の教育が目指すべき未来
ハミルトンの事例は、私たちに「共生」という理念を改めて問いかけます。彼らが実践する「包摂的個別対応」は、教える側の障がいへの深い理解と、個々のニーズに応じた柔軟な配慮がなければ実現できません。
特に、特別支援教育を専門とする教員だけでなく、すべての教員が、子ども一人ひとりの特性を理解し、その子に合ったサポートを考える姿勢が求められます。また、ハミルトンのように**「特別支援アシスタント」の制度をさらに広げていく**ことは、現場の負担を軽減し、より手厚い個別支援を実現するための鍵となるでしょう。
まとめ
日本の教育も、専門的な支援を否定するのではなく、「共生」という理念を基盤に、より良い形を模索していく必要があるのではないでしょうか。ハミルトン教育の実践は、そのための具体的なヒントを与えてくれます。私たち一人ひとりがこの問いに向き合うことで、真のインクルーシブな社会への道が開かれるのかもしれません。
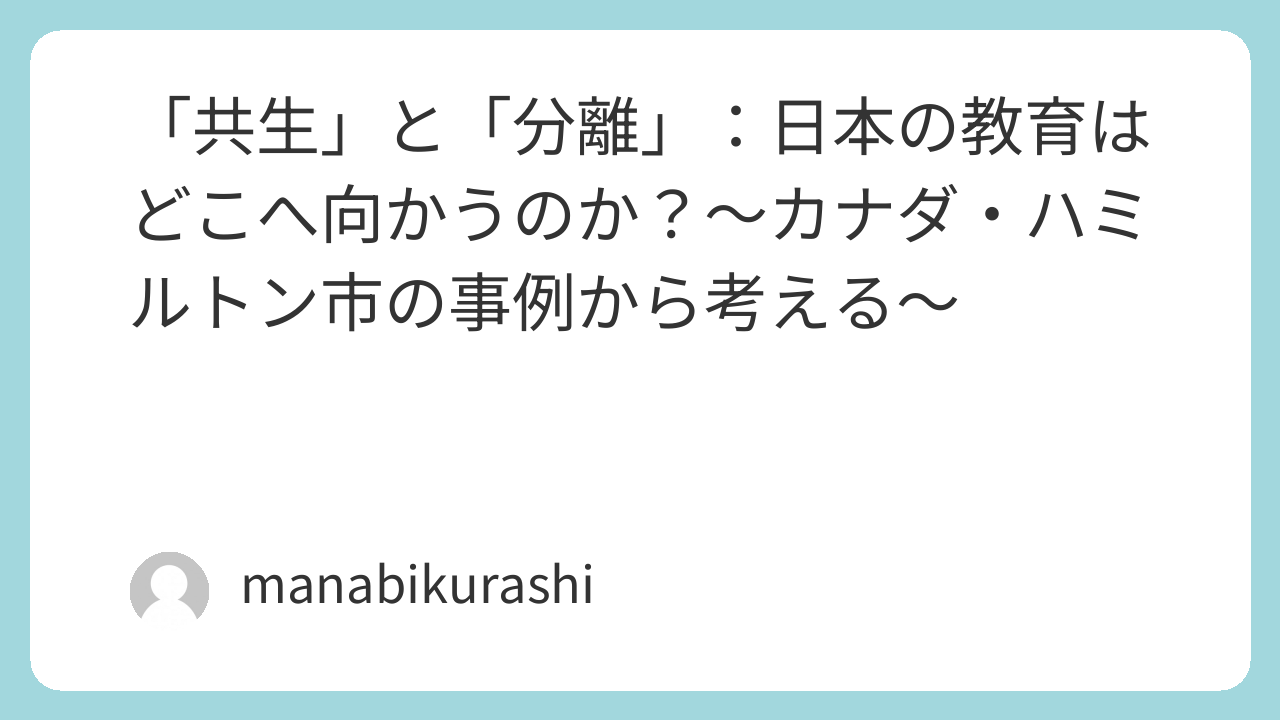
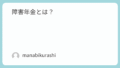

コメント