ポリヴェーガル理論:子どもたちの行動を理解し、支援する新しい視点🌈
「困った行動」はサバイバルのサイン:ポリヴェーガル理論が示すこと
ステファン・ポージェス博士の提唱したポリヴェーガル理論は、「脳と身体は双方向で連携し、私たちの生存と成長を助けている」という画期的な仕組みを明らかにしました。これにより、私たちが「問題行動」と捉えがちな子どもたちの行動が、実はその子の**神経系が必死に状況に適応しようとしている「生存反応」**であると、肯定的に捉えることが可能になりました。
この理論によれば、人間は絶えず変化する環境に対し、生き残り、そして最終的に繁栄するために進化の歴史に基づいた適応的な反応を示しています。これは、私たちの神経系がストレスや環境からの手がかりに応じて、常に体の反応を調整している様子を表しています。
私たちは、これらの生存反応を、進化的な階層を持つ以下の3つの状態で理解します。
- 社会交流(緑)🟢: 安全な状態。落ち着き、つながり、共感。
- 防衛(赤)🔴: 危険を感じた状態。闘争(かんしゃく、反抗)や逃走(逃げ出す、落ち着きがない)反応。
- 生命の危機(青)🔵: 極度の危険を感じた状態。シャットダウン(無気力、解離、フリーズ)。
キーワードで読み解く新しい行動理解:ニューロセプションとボトムアップ
従来の**「医療モデル」では、子どもたちの行動課題を症状の集まりと見なし、「治療すべき障がい」と捉えがちでした。しかし、ポリヴェーガル理論は、行動そのものではなく、その行動を引き起こしている根本的なプロセス**に焦点を当てます。
1. 無意識の安全検知:ニューロセプション
子どもたちの行動の背後にあるのは、**ニューロセプション (Neuroception)**と呼ばれるプロセスです。
これは、私たちが意識的に「安全だ」「危険だ」と判断する前に、神経系が自動的・無意識的に環境の手がかり(声のトーン、表情、周囲の音など)を検知し、自身の状態を**「緑・赤・青」のいずれかにセットする「安全検知器」**のようなものです。
- 例えば、突然大きな音を聞くと、論理的に考える前に体がこわばります。これは、神経系が「危険(赤)」と判断したサインです。
- 子どもが不安や恐怖を感じて突然大声を出したり固まったりするのは、その環境や状況がその子の神経系にとって**「危険」または「生命の危機」**とニューロセプションされた結果なのです。
2. 身体からの信号が優先:ボトムアップとトップダウン
ポリヴェーガル理論に基づく理解では、行動の調整は**「ボトムアップ」(身体・神経系→脳)が「トップダウン」**(脳→身体・論理)に優先します。
- 子どもがパニック(赤や青の状態)にあるとき、どれだけ**論理的な言葉(トップダウン)**で「落ち着きなさい」と言っても、神経系のサバイバルモードは解除されません。
- このとき必要なのは、**身体(ボトムアップ)**に「安全」であることを伝えることです。穏やかな声のトーン、安心させる表情、ゆっくりとした呼吸など、「社会交流(緑)」を活性化する信号を送ることで、神経系をまず落ち着かせることが、論理的な思考や行動調節への第一歩となります。
3. ニューロダイバーシティへの優しいまなざし:個人差の理解
ポージェス博士の理論は、すべての子どもが**「生存と繁栄を目指す」という同じ原動力を持っていることを示しています。しかし、その環境への適応の仕方や、ニューロセプションの敏感さには大きな個人差**があります。
- 発達の違いのある子どもたち、いわゆるニューロダイバーシティを持つ子どもたちは、定型発達の子どもたちと比べて、ニューロセプションの閾値が異なったり、環境の変化をより強く「危険」として捉えやすかったりすることがあります。
- この個人差を理解することで、私たちは子どもたちの行動を「できないこと」「治すべきこと」ではなく、「その子の神経系が、今の環境に必死に適応しようとしている、ユニークで適応的な反応」として捉え直すことができます。
この新しい視点により、私たち大人(親、教師、支援者)は、子どもたちの行動を変えさせようとする前に、まず環境と私たち自身が「安全(緑)」の信号を送れているかを見直すことができます。診断名ではなく、子どもたちの神経系の状態を読み解くことで、心と体に寄り添ったサポートが可能になるのです。
モナ・デラフーク著の「発達障害からニューロダイバーシティへ」を読み、少し紹介しました。学校の中で問題とされる行動をまた別の視点から考えられる素晴らしい考え方でしたので、ぜひ教育現場や子育てをする上で参考にできればと思います。次回はこの知識をどのように活用していくか考えていきたいと思います。
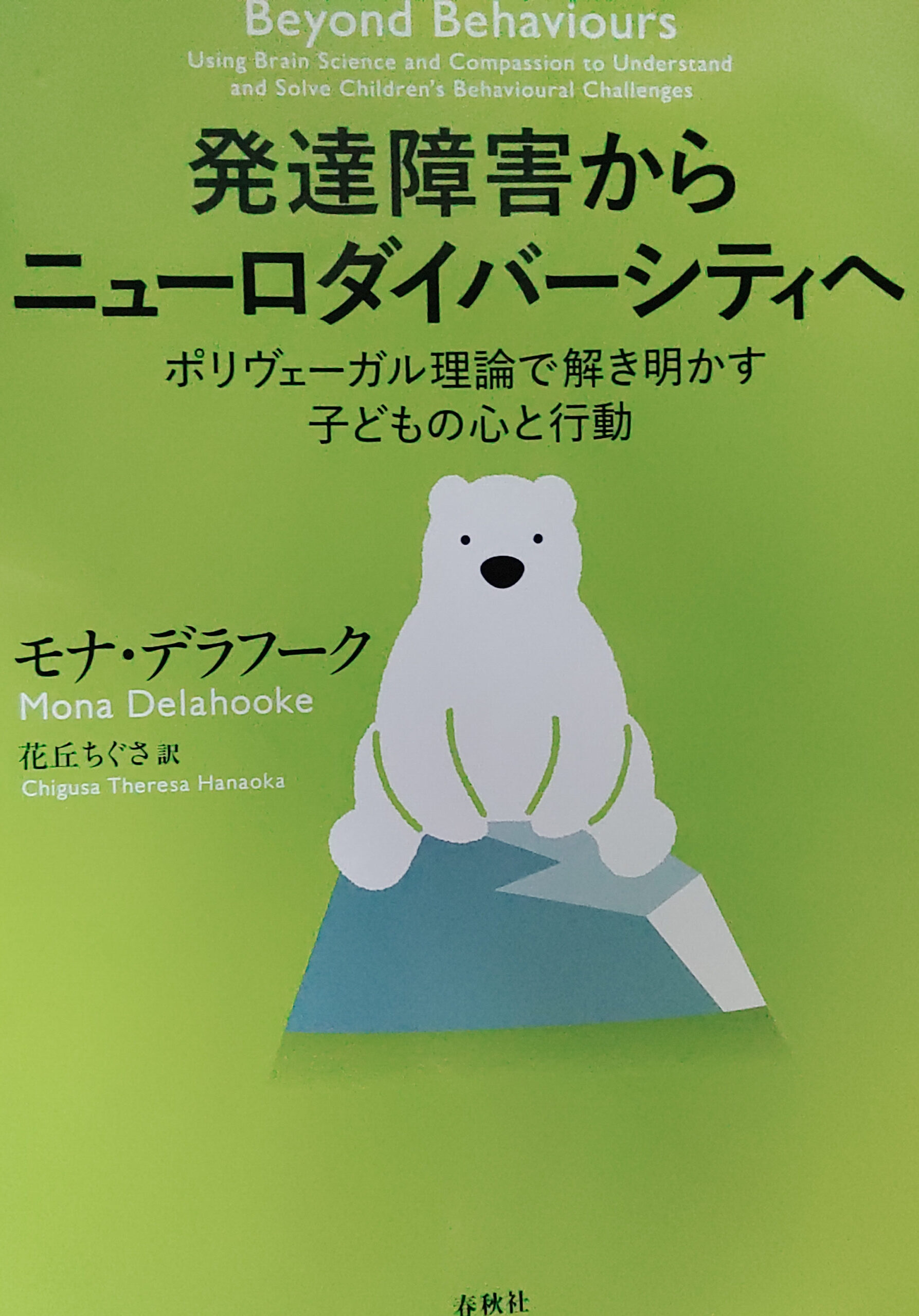
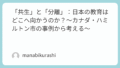

コメント